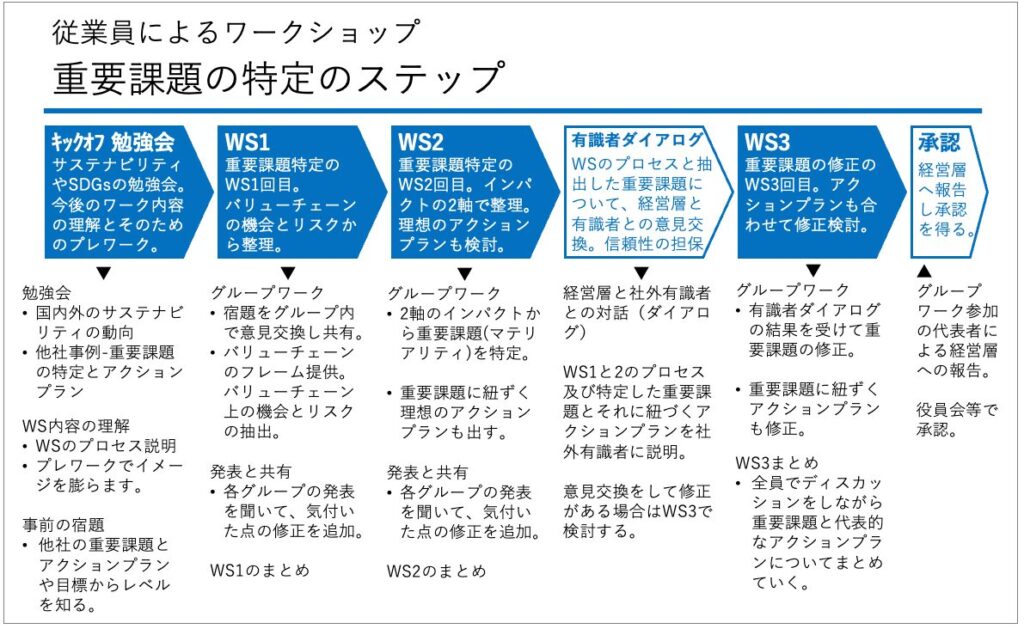第5回 佐藤製薬の新入社員SDGs研修はアイデアの宝庫
サステナビリティやSDGsを新入社員研修に取り入れる企業は多いことでしょう。でも、半日という短い時間で「社会課題の理解」と「自社の深いインプット」、そして「アウトプットの楽しさ」まで一気に体験させる研修は、実はなかなかありません。
佐藤製薬の新入社員SDGs研修は、主力製品の調査から新製品アイデアづくり、プレゼン発表までを駆け抜ける実践型プログラム。学生時代の感性をそのまま生かしながら、仲間と話し合い、企画を組み上げていく姿は毎年本当に見事で、「学びのつくり方」の巧みさが光ります。本稿では、そのユニークな仕組みと魅力をご紹介します。
(続きはリンクへ)